
昨今、ある時代特有の文化や様式をブームとして取り上げられることが多いなと感じます。例えば、「昭和レトロ」や「大正ロマン」、「平成ポップ」(平成ポップ・・・?)などが挙げられます。古ければ良い、歴史が長ければ良いわけでは無いですが、やはり世界最古と聞くと心が踊ります。世界最古で、しかも、それが日本にあるとなれば行ってみたくなるのが人の性かと思います。

そこで今回、世界最古の木造建築物と言われ、ユネスコに世界文化遺産として認定された、奈良県にある「法隆寺地域の仏教建造物」に行ってみました。(何年か前ですが・・・)世界遺産についても、このブログ記事で触れていこうかと思っていますので、過去に行った時の情報と最新情報踏まえ、言わずと知れた世界最古の木造建築群を紹介していければと思います。
日本史でTOP3に入るであろう超有名偉人である「聖徳太子」ゆかりのこの地で、実際に千年以上の時を刻んできた建物を見て、何を感じ、何を思っていたのか。その時の様子を紹介していきたいと思いますので、最後まで読んでいただけたら嬉しいです!!!
Contents
法隆寺とは?世界で評価されたポイントは?

法隆寺は、奈良県生駒郡斑鳩町に位置するお寺で、推古15年(西暦607年)に
聖徳太子と推古天皇によって創建されたと伝えられており、日本を代表する仏教寺院です。
1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」として、白神山地、屋久島、姫路城とともに、
日本で最初の世界遺産のひとつとして登録されました。
ユネスコ世界文化遺産として登録され、登録項目は次の4項目です!
(i)人間の創造的才能を表す傑作である。
(ii)建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
(ⅳ)歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
(ⅵ)顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
「法隆寺地域の仏教建造物」登録範囲には、法隆寺の建造物47棟と
法起寺の三重塔を加えた48棟が含まれています!
有名な「金堂」や「五重塔」、「中門」が建ち並ぶ西院伽藍のほか、夢殿を擁する東院伽藍、そして周辺の関連建造物も含まれています。中でも「五重塔」は、現存する木造建築としては世界最古とされており、約1400年の歴史と悠久の時への浪漫を感じることができます。
いざ法隆寺へ!東京からのアクセスは?

皆さんがこの記事を見て頂いて、少しでも法隆寺への興味を持って頂けたら嬉しいです。
そんな法隆寺へのアクセスについて、ご紹介します!!
私が首都圏在住なので、東京駅から行くルートとして、
おすすめなルートは、新幹線+JRで行く約3時間のルートになります。
ルート概要
東京駅 → 新大阪駅(東海道新幹線)
新大阪駅 → 法隆寺駅(JR在来線乗り継ぎ)
JR法隆寺駅北口から徒歩なら約20分です。
詳細手順
① 東京駅から東海道新幹線で「新大阪駅」へ(のぞみで約2時間30分)
② 新大阪駅でJR在来線(大阪環状線→大和路線)に乗り換え、「法隆寺駅」下車(約40〜50分)
③ 法隆寺駅から徒歩で約20分、または奈良交通バス(「法隆寺前」停留所)でアクセス可能です。
また徒歩で行く場合には、駅前から少し歩くと、住宅街を抜け県道5号線たどり着きます。
再び住宅街に入り、だんだんと門前町のような雰囲気に包まれてきます。
しばらく歩くと法隆寺の南大門が目に飛び込んで来ます。
料金目安
片道:約15,000円(指定席利用)となります。
もちろん夜行バス等を使用すれば、旅費は抑えられるかなと思います!
実際に法隆寺を参詣した感想

私が法隆寺に行ったのは、大学4年生の時でした。その当時は、法隆寺の歴史的背景を綿密に調べずに法隆寺に行ってしまったため、表面的なところしか見て回れていないのですが、やはり「世界最古の木造建築物 五重塔」は、到着後一番に見に行きました・・・(笑)
五重塔を拝見した感想は、写真で見るよりも下から覗きこむと、段が上がるにつれて各層の重が小さくなっていくのが、美術で使用する遠近法のお手本みたいだな・・・でした。(笑)
中にある心柱については、見れてはいません。普段から見れるものでも無いですし・・・。ただ心柱を用いる建築技術は、東京スカイツリーを建造する際にも採用されたと知っていたので。古の職人技術を見れなかったのは残念でした。
すぐ横には、国宝である「金堂」がありました。(上記写真だと、手前の建造物です)金堂は西院伽藍最古の建築物と言われており、二重の屋根が印象的でした。金堂の内部についても撮影をしたかったのですが、撮影禁止でした。(確かここは見れなかった気がします・・・写真無くて昔なので、記憶があやふやです。すみません)
大講堂については、完全に全体を収めた写真のみですが、中にある国宝の「薬師三尊像」についても、見れる機会があれば見に行きたいなと思います。完全に次回の話ですが・・・(笑)

「法隆寺地域の仏教建造物」ですが、行った後に調べてしまい後悔ですが、レアな建築方法がいたるところで採用されています。そもそも1000年以上前の木材は、そのままの頑丈さを持っていることも、冷静に考えたらとんでもない事だなと・・・(感想浅いですが)
当時の宮大工が持っていた技術に、敬意を払って次回以降は、参詣しに行こうかなと思います。
昔「正岡子規」の有名な俳句である「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」、正岡子規が法隆寺に立ち寄った後、茶店で一服して柿を食べると、途端に法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じたと言われており、次回は秋に行って、また皆様に詳細をお伝えできればなと思います。
これから行く人へ

実際に興味を持たれて訪れるなら、朝の早い時間帯がおすすめです。
観光客が多くなく、比較的参詣しやすいです。
足元は砂利道や石畳が多いので、ヒールが高いくつとかは歩きにくいかもしれないです。
西院伽藍から、東院伽藍夢殿まではやや距離があるので、水分補給も忘れずに。
同じ奈良県内で、「古都奈良の文化財」と登録されている世界文化遺産があります。
ぜひ時間に余裕をもって、奈良県全域を散策してみてください。

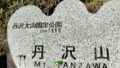

コメント